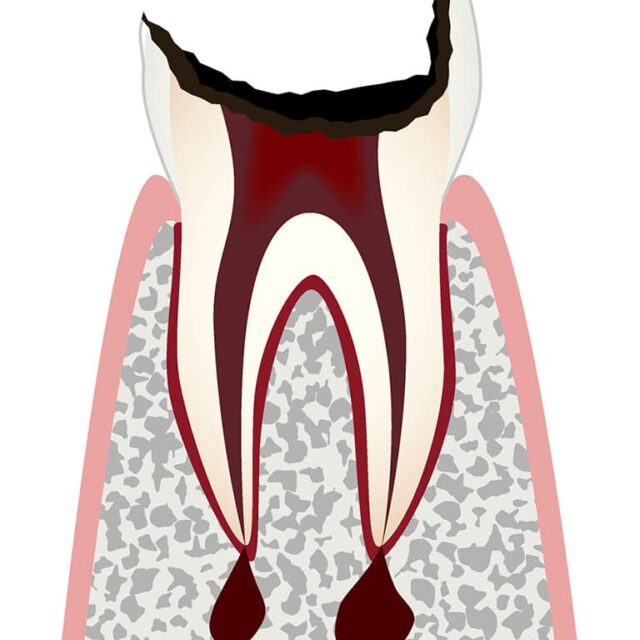目次
顎関節症の症状とセルフチェック法|歯科でできる効果的な治療法とは
こんにちは。松本市の歯医者、平沼歯科医院です。
今回は多くの方が感じているであろう、これって顎関節症?なんでなるんだろう?といった疑問を解決できるような記事を作成しました。少しでも参考になれば幸いです。
顎関節症とは?
顎関節症とは、顎の関節(※耳の前にある顎関節)やその周囲の筋肉に痛みや違和感が生じたり、口の開閉に支障が出る症状の総称です。硬いものを噛んだときや大きく口を開けたときに顎が痛む、口を開けると「カクッ」と音がする、といった経験はありませんか?こうした症状がみられる場合、顎関節症の可能性があります。子どもから高齢者まで誰にでも起こり得るトラブルですが、顎関節症は早めに対処すれば重症化を防ぎ、日常生活への影響を最小限にすることができます。
顎関節症は一つの病気を指す言葉ではなく、顎関節や咀嚼筋(噛むための筋肉)などに関連するさまざまな異常状態をまとめた総称です。その病態には、顎の関節を構成する軟骨(関節円板)のずれや損傷、顎を動かす筋肉の障害、関節を支える靭帯の異常、変形性関節症(関節の変形やすり減り)などが含まれます。要するに「口を開けにくい・顎が痛い・音が鳴る」などの症状を引き起こす顎周りの不調全般を指して顎関節症と呼んでいるのです。
顎関節症の症状
顎関節症の代表的な症状には、次のようなものがあります。
・顎の痛み(顎関節痛):耳の直前あたりにある関節や、その周囲が痛む。口を開けたり物を噛んだりすると痛みが強くなることもあります。場合によってはじっとしていても鈍い痛みや違和感を感じることもあります。
・関節音(クリック音):顎を動かすと「カクッ」「パキッ」といった音が関節から聞こえる。ときには砂利を踏むようなジャリジャリした音や、軋むような音がするケースもあります。この音自体には痛みが伴わない場合もありますが、顎関節症のサインの一つです。
・開口障害(こうこうしょうがい):口を大きく開けられない、開けようとすると顎関節が引っかかる感じがして途中で止まってしまう、といった状態です。通常、縦に指が3本入る程度(約4cm程度)口を開けられますが、開口障害があると指2本分ほど(約2~3cm)しか開かないこともあります。また、口を開け閉めする際にスムーズに動かず、下顎が左右どちらかにずれてしまうこともあります。
・顎の疲労感・こわばり:長時間ものを噛んでいると顎がだるく疲れてしまう、朝起きたときに顎がこわばって開けづらい、といった筋肉の疲労症状です。就寝中の歯ぎしりや食いしばりが原因で起こることがあります。
・関連する症状:顎の不調に伴い、頭痛や首・肩のこり、耳の痛み(耳鳴りや耳の閉塞感を感じることも)を引き起こす場合もあります。顎は頭部や首とも近いため、顎の不具合が周囲に波及してこうした症状を招くことがあります。
個人により症状の現れ方は様々で、痛みはないが音だけ鳴るという軽いケースから、痛みが強く口がほとんど開かない重度のケースまで幅があります。ただし一般的には、顎関節や耳の前の痛み・不快感、口の開けにくさ、顎を動かすときの音、といった症状が顎関節症の典型例です。思い当たる症状がある場合は、後述するセルフチェックや対処法を参考にしつつ、早めに歯科医院で相談することをおすすめします。
顎関節症のセルフチェック方法
「もしかして顎関節症かな?」と思ったら、自分で以下のポイントをチェックしてみましょう。当てはまる項目が多い場合は、顎関節症の可能性があります。
・口の開閉時の痛み:ゆっくり口を開け閉めしてみて、耳の前あたりに痛みや違和感がありませんか? あくびをしたときや大きな声で話したときに顎が痛む場合もチェックポイントです。
・顎関節の音:口を大きく開けたり、左右に顎を動かしたときに「カクッ」あるいは「ミシッ」という音が鳴りませんか? 指先を耳の前の顎関節に当てて開閉すると、音や振動を感じとりやすいです。
・口の開き具合:人差し指・中指・薬指の3本の指を縦に揃えて口に入れてみてください。正常なら指3本が楽に入りますが、痛みや引っかかりで指2本程度しか入らない場合、開口障害の可能性があります。
・噛みしめの癖:上下の歯を強く噛みしめる癖が日常生活でありませんか? ふと気づくと歯を食いしばっている、寝ている間に歯ぎしりを指摘されたことがある、といった場合は顎関節に負担がかかっています。
・顎の位置のずれ:ゆっくり口を開けたとき、下顎がまっすぐ下に降りていますか? 開け始めや閉じ終わりで顎が左右どちらかにずれる場合も、関節や筋肉のバランスが崩れているサインです。
・朝の顎のだるさ:朝起きたときに顎がだるい、筋肉痛のような痛みを感じる場合は、睡眠中に歯ぎしり・食いしばりをしている可能性があります。これも顎関節症の一因となります。
いかがでしたか? 以上のセルフチェック項目で一つでも当てはまるものがあれば、顎関節症の疑いがあります。早めに歯科医院や専門の口腔外科を受診し、専門家による診断を受けましょう。軽度のうちに対処することで、症状の悪化を防ぐことができます。
顎関節症の原因
顎関節症は原因が一つに特定できる場合もあれば、複数の要因が重なって起こる場合もあります。また症状の種類によって原因が異なることもあります。一般的に認識されている主な原因は次の通りです。
・噛み合わせの異常(不正咬合):上下の歯のかみ合わせがずれていると、顎関節に不自然な力がかかります。例えば、歯並びの乱れや欠損歯放置、詰め物・被せ物の高さ不良などにより噛み合わせが悪いと、顎の動きに無理が生じて関節や筋肉へ負担が蓄積します。
・生活習慣や癖:歯ぎしり(ブラキシズム)や歯の食いしばり、片側ばかりで噛む癖、頬杖をつく、うつ伏せ寝をする、といった日常の癖・習慣は顎関節症の大きな要因です。特に就寝中の歯ぎしりは自分では気づきにくいですが、長期間続くと顎関節や歯に大きな負担を与えます。
・ストレス・心理的要因(心因性):精神的なストレスが強いと無意識に顎に力が入ったり、歯をぐっと噛み締める癖が出ることがあります。緊張で顎周りの筋肉がこわばり続けると、筋肉の痛みや関節の不調につながります。現代社会ではストレス性の顎関節症も少なくありません。
・外傷や過度な負荷:顎に強い衝撃を受けた事故や怪我、硬いものを無理に噛んだり大きく口を開けすぎたりしたことで関節が傷つくケースです。一度の外傷で発症することもあれば、その後遺症で関節が変形して慢性的な痛みを抱えることもあります。
以上のように、噛み合わせの問題・習慣的な要因・ストレス・外傷などが顎関節症の主な原因です。実際にはこれらが複合的に絡み合って症状が出ることも多いです。例えば、もともと軽度の噛み合わせ異常がある人がストレスで歯ぎしりが増え、その結果顎関節症を発症するといったケースもあります。
なお、10代~30代の女性に顎関節症が多い傾向があるとも言われます。これには女性ホルモンの影響や関節の柔らかさの違い、男性より筋力が弱いため関節に負担がかかりやすいことなどが関係している可能性があります。ただし顎関節症は男性にも高齢者にも起こり得るため、「自分は違う」と油断せず、症状があれば適切に対処することが大切です。
顎関節症の治療法(歯科で行う主な治療)
顎関節症の治療は症状の程度や原因に合わせて選択されます。軽度であれば生活習慣の見直しや一時的な安静(顎を休めること)で改善するケースもありますが、症状が続く場合は歯科医院での専門的な治療が有効です。歯科で行われる主な治療法として、「マウスピース治療」「バイトプレート治療」「噛み合わせ治療」が挙げられます。それぞれの治療法の概要と特徴を詳しく見ていきましょう。
マウスピース治療(スプリント療法)
この治療は非侵襲的(体に侵襲を与えない)かつ可逆的という利点があります。つまり、マウスピースを装着するだけで歯や顎の形そのものは変えないため、必要に応じて中止したり調整したりが容易です。噛み合わせをいきなり削ったり矯正したりする前にまず試す保存療法として、多くの歯科医が第一選択に挙げる治療法です。マウスピース装着により一時的に噛み合わせが均等になり症状が軽減するケースも多く報告されています。
なお、マウスピースの装着中は多少の違和感を伴うことがありますが、徐々に慣れていきます。また、定期的に歯科医でマウスピースの噛み合わせ状態をチェックし、必要に応じて調整を行います。素材はプラスチックなので経年的にすり減ったり割れたりすることもありますが、その場合も新しく作り直すことが可能です。
噛み合わせ治療(咬合の改善)
噛み合わせ治療(咬合調整・咬合治療)は、顎関節症の原因が歯の噛み合わせの不良によるものと診断された場合に行われる治療です。具体的には、上下の歯の当たり方を理想的な状態に近づけることで、顎関節への偏った負荷を減らすことを目指します。
噛み合わせ治療の方法にはいくつかあります。比較的軽度のケースでは、歯科用の紙(咬合紙)で歯の当たり具合を確認しながら、高すぎる詰め物や歯の一部をわずかに削って調整する処置が行われます。これにより噛み合わせのバランスを整え、顎の動きをスムーズにします。また、歯の位置関係に大きな問題がある場合には、矯正治療によって歯並び自体を改善したり、被せ物・ブリッジなど補綴治療で噛み合わせを再構築したりすることもあります。
重要なのは、噛み合わせ治療を行う前に本当に噛み合わせが原因かを正確に見極めることです。もし原因が噛み合わせにあれば、この治療によって症状が大きく改善する可能性があります。実際、診断が的確に行われ原因となる不正咬合の部位を特定できた場合、その改善を目的とした治療は高い効果を発揮することが知られています。しかし、原因でない歯を削ったり大きく噛み合わせを変えたりしてしまうと、かえって症状が悪化するリスクもあります。
そのため現在では、まずマウスピースなどで様子を見て、それでも症状が残る場合に噛み合わせ治療を検討するという流れが一般的です。歯を削る処置は一度行うと元に戻せないため、必要最小限に留めながら慎重に進めます。歯科医師は咬合分析という詳しい検査を行い、どの歯がどの程度当たっているか、顎の動きに問題がないかを調べた上で治療計画を立てます。
その他の治療法(薬物療法・外科的治療など)
多くの顎関節症は上記の保存療法(マウスピースや噛み合わせ調整など)で改善しますが、症状や原因に応じて他の治療が併用されることもあります。
・薬物療法:痛みや炎症が強い場合には、鎮痛剤(消炎鎮痛薬)や筋肉の緊張を和らげる筋弛緩薬が処方されることがあります。一時的に痛みを和らげることで食事や睡眠を取りやすくし、その間に他の治療効果を高めます。長期的な内服は避け、症状が落ち着いたら中止します。
・理学療法:指導のもとで行う顎のリハビリテーションです。具体的には、顎周辺のマッサージやストレッチ、関節運動の訓練などがあります。温熱療法(あたためる)や低周波治療で筋肉の血行を良くし、痛みを軽減する方法もとられます。自宅でもできる簡単な顎の運動を教わり、毎日実践することで徐々に可動域を拡大したり痛みを和らげたりします。
・外科的治療:ごく一部の重症例では外科手術が検討されます。例えば、関節内部に溜まった炎症物質を洗い流す関節腔洗浄や、ずれて戻らなくなった関節円板を整復する手術、変形してしまった関節を再建する手術などです。ただし手術が必要になるケースは稀で、多くは保存療法で十分対応可能です。手術の適応かどうかは専門の口腔外科医が慎重に判断します。
各治療法にはそれぞれ利点があります。症状や原因に応じて、これらの治療法を単独で行ったり組み合わせたりして治療計画が立てられます。例えば、まずマウスピースで様子を見つつ並行して生活習慣を改善し、症状が治まらなければ噛み合わせ調整を追加するといった具合です。大切なのは、患者さん一人ひとりの状態に合わせて最適な方法を選択することです。
日常生活でのセルフケアと予防策
顎関節症の治療と並行して、日常生活でできるセルフケアや予防策にも取り組みましょう。ちょっとした工夫で顎への負担を減らし、症状改善を助けたり再発予防につなげたりできます。
・硬いもの・大きすぎるものを避ける:せんべいや硬いスルメのような食べ物、極端に大きなハンバーガーなど口を無理に開かなければならない食品は控えめに。食材はなるべく小さく切り、一口で無理なく噛める大きさにしましょう。
・片側だけで噛まない:食事の際に左右どちらか片方ばかりで噛む癖があると、顎関節にかかる力が偏ります。意識的に左右均等に使って噛むように心がけてください。
・悪い姿勢・癖の見直し:頬杖をつくと下顎がゆがんだ位置で固定され、顎関節に負担がかかります。長時間のスマホやPC作業でうつむき姿勢が続くのも顎に良くありません。時々姿勢を正し、顎や首周りを動かして緊張をほぐしましょう。歯を食いしばっていないか気づいたときには力を抜く習慣も大切です。
・顎のストレッチ:痛みが強くない範囲で、顎の簡単なストレッチや運動を行うと効果的です。例えば口をゆっくり「縦に」開閉する運動や、左右の顎関節に指を当てながら下顎を前後左右にゆっくり動かす練習などがあります。お風呂上がりなど筋肉が温まっているときに無理のない範囲で行いましょう。ただし痛みが出る場合は無理しないでください。
・ストレスのケア:精神的なストレスを感じるときは、深呼吸や軽い運動などでリラックスを心がけ、就寝前にもリラクゼーションを取り入れてみましょう。睡眠の質を上げることも歯ぎしりの軽減につながります。
これらのセルフケアはあくまで補助的な対策ですが、習慣化することで顎関節症の改善・予防に役立ちます。特に治療中の方は、治療効果を高めるためにも日常で顎を労わる工夫を続けてください。
まとめ
顎関節症は「顎が痛い」「口が開かない」「顎から音がする」など日常生活に支障をきたすつらい症状を引き起こします。しかし、適切なセルフチェックで早期に気付き、歯科での専門的な治療や日常でのセルフケアを行うことで、多くの場合は症状をコントロールし改善することが可能です。
特にマウスピース治療は、顎関節や歯への負担を和らげるシンプルかつ効果的な方法です。噛み合わせに問題がある場合には、必要に応じて噛み合わせ治療を行うことで根本的な改善が期待できます。それぞれの治療法にはメリット・デメリットがありますが、歯科医と相談しながら自分に合った方法で進めることが大切です。
「もしかして顎関節症かも?」と思ったら、ぜひ今回ご紹介したセルフチェックを試し、早めに専門医に相談しましょう。顎の痛みや不調を我慢し続ける必要はありません。適切なケアによって、食事や会話を再び快適に楽しめるようサポートいたします。顎関節症とうまく付き合い、笑顔で過ごせる毎日を取り戻しましょう。
🦷平沼歯科医院|松本市の予防歯科・一般歯科・小児歯科
📞ご相談・お電話はこちらからどうぞ!